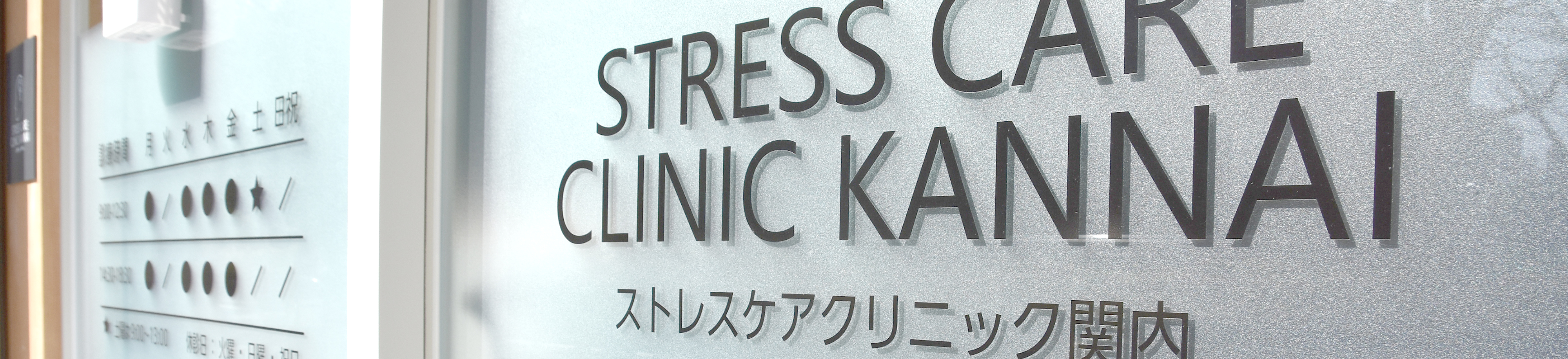
診療案内SERVICE
うつ病

- 漠然とした不安を感じる
- 仕事などに集中できない
- 楽しいと思えることがない など
うつ病は「気の持ちよう」で発症・治癒する病気ではありません。早めに専門的な治療受けることが大切です。患者さまによって治療法はそれぞれことなります。患者さまの症状やお悩み、治療へのご要望などを確認して、治療を進めていきます。抗うつ薬にはさまざまな種類があるので、患者さまの症状や状態に応じて使い分けます。効果が現れるまでに1週間から数週間程度かかりますので、まずは焦らずに飲み続けましょう。
うつ病の症状と治療
治療にあたっては、まずは病気について理解していただき、どのような治療が必要なのかを知っていただくことが大切です。その上で、ストレスになっている出来事や周囲のサポートを確認して、療養できる環境を整えることや、抗うつ剤を基本とした薬物治療や精神療法を組み合わせて治療していきます。
双極性障害

- 気分の高揚感が強い
- 夜に眠らなくても平気で過ごせる
- 気が散って集中できない
- 借金をしてまで買い物をしてしまう など
かつて「躁うつ病」と呼ばれていた病気で、気分が高揚する「躁状態」と、気分が落ち込んでしまう「うつ状態」が強く交互にやってきます。治療は薬物療法が基本で、一般的には「気分安定薬」という種類のお薬で症状を緩和していきます。気分の幅が大きく乱れた状態を安定させる働きがあるため、躁状態とうつ状態のどちらにも有効です。こうした薬物療法と併行して、精神療法を行うこともあります。
パニック障害

- 突然激しい動悸が起こる
- 過呼吸を起こす
- 身体が震えて止まらない
- 「死んでしまうのではないか」と強い恐怖心を抱く など
何も起きていない状態で突然何の前触れもなく、激しい動悸やめまい、発汗、窒息感、手足の震えなどの発作(パニック発作)が起こります。パニック発作が繰り返されると、それを恐れることで、電車に乗れない、外出できない、など日常生活に支障が出るようになります。パニック発作自体は一生のうちに1度起こす人が多いですが、パニック発作を繰り返すと「パニック障害」へ発展していきます。QOL(生活の質)が下がってうつ病などを併発することもあるため、早期治療が必要です。
パニック障害の治療
適応障害

- 不安・無気力・倦怠感
- 思考力・集中力の低下
- イライラ・悲壮感・焦り
- 不眠・食欲不振・動悸・過呼吸 など
適応障害は、新しい社会環境に対応することができず、不安感や抑うつ状態、対人トラブルなど、さまざまな症状や問題が起こり、社会生活に支障をきたす病気です。就学や就職、転職、結婚、離婚など、生活環境が大きく変わった時によく見られます。治療には、まず原因となるストレスを軽減するため、環境を調整して適応しやすく整えていきます。環境変化が難しい場合は、「認知行動療法」や「問題解決療法」を行います。この他、抗不安薬や抗うつ薬などを使用することもあります。
適応障害とうつ病の違い
適応障害の治療
自律神経失調症

- 微熱が続く
- 頭痛、肩こり、手足のしびれが続く
- 息苦しさ、動悸、めまい、立ちくらみ、耳鳴り
- 食欲低下、イライラ、不安 など
自律神経は、交感神経と副交感神経から成り立っており、呼吸・体温・血管・内臓などの動きをコントロールしています。通常は交感神経と副交感神経がバランスを取りながら働きますが、ストレスや疲労、ホルモンバランスの乱れ、不規則な生活などにより、バランスが崩れてさまざまな症状が起こるのが自律神経失調症です。治療は、抗不安薬や抗うつ薬などによる薬物療法や、カウンセリングなどです。また、規則正しい生活、栄養バランスのとれた食事を摂る、適度な運動といった生活改善も大切です。
社会不安障害
(あがり症、赤面症)
(あがり症、赤面症)

- 人前に出るととても緊張する
- 手足や全身、声のふるえが起きる・顔がほてる
- トイレが近くなる、または尿が出なくなる
- めまいがする など
初対面の人と話をしたり、職場や学校などで対人関係を強いられたりすると、過剰な不安や緊張を感じて、動悸や震え、吐き気などの身体症状が出ることがあります。それが出社・登校拒否になってしまうほど強く現れる場合は、社交不安障害の可能性があります。社交不安障害は、脳内の神経伝達物質を調節できないことで起きると考えられています。そのため治療には、抗不安薬や抗うつ薬の投与で脳の機能を調整する薬物療法や、物事に対する考え方や捉え方、行動などを変えるための認知行動療法を行います。
あがり症は性格? 社会不安障害?
不眠症

- 横になってもなかなか眠れない
- 夜中に起きてしまい、また眠ることができない
- 朝早く目が覚めてしまう など
不眠症にはいくつかのタイプがあり、なかなか寝つくことができない「入眠障害」、途中で何度も目が覚めてしまう「中途覚醒」、早朝に目が覚めてしまう「早朝覚醒」、眠りが浅く眠った感じがしない「熟眠障害」などがあります。人によって適切な睡眠時間は異なりますが、十分な睡眠が取れず、生活や心身に支障をきたしている状態であれば、不眠症と判断されます。不眠症の原因は多岐にわたり、ストレスや悩みなどの心理的要因、生活リズムの乱れや加齢などの生理的要因、心身の病気によるものなどさまざまです。
不眠症の治療
統合失調症

- 誰かが自分の悪口を言っていると思い込む
- 自分には見えているものが、他人から「見えない」と言われたことがある
- 誰かが自分のことを陥れようとしていると感じる
- 他人から「話にまとまりがない」と言われたことがある など
統合失調症は、脳の神経ネットワークに何らかの障害が起こることで生じ、15~30歳ごろの思春期から青年期に発症するケースが多く見られる病気です。初期段階では、親への反抗、不機嫌、成績の低下、友人との交流減少などが見られ、徐々に幻聴や妄想などの特徴的な症状が出現してきます。治療は症状に応じて、抗精神病薬や睡眠薬や抗不安薬、気分安定薬などの薬物療法を行います。また、精神科リハビリテーションを併用することも多くあります。
強迫性障害
(強いこだわり)
(強いこだわり)

- 外出したのに、ドアをきちんと施錠したか心配になって家に戻ってしまう
- 窓や玄関の鍵、ガス栓などが閉まっているか不安になり、何度も確認してしまう
- 自分の手が汚れていると感じて、何度も手を洗ってしまう など
自分の意思に反して不合理な考えに強くとらわれ、不安を打ち消すために無意味な行動を繰り返してしまう病気です。治療は、薬物療法と精神療法が中心となります。このうち薬物療法では、主に「SSRI」というお薬を使用しますが、重症の場合は少量の抗精神病薬を併用します。精神療法では、患者さまに強迫症状が出やすい場面に立っていただき、強迫行為を行わないように指示します。最初は不安を感じますが、徐々に不安感が消えていくことが期待できます。
認知症
(物忘れ)
(物忘れ)

- もの忘れがひどい
- 時間や場所がわからなくなることがある
- 判断・理解力が低下した など
加齢とともにもの忘れが起こるのは自然なことで、脳の老化によるものです。しかし認知症は脳の病気で、加齢によるもの忘れとは異なります。認知症が進行すると、理解力や判断力が低下していき、日常生活に支障が出るようになります。シニアの方に多いですが、認知症の種類によっては30代から発症するものもあります。年齢に関わらず、認知症になったら早期に治療を開始することで、進行をかなり遅らせることができます。
産後うつ

- 育児がつらい
- 涙もろい
- 怒りっぽい
- 子どもを育てていく自信がない など
産後の女性は、ホルモンの急激な変化や、出産そのものによるストレス・疲労などにより、情緒が不安定になりやすい状態です。このため約3割の女性は、産後すぐに涙もろさや不安定な気分、イライラなどを経験します。多くの場合は一過性で自然に回復しますが、この状態が2週間以上続く場合は、産後うつと診断されます。決してめずらしい病気ではなく、母子双方に深刻な影響を及ぼす可能性があるため、無理せず早めにご相談ください。
アルコール使用障害
(アルコール依存症)
(アルコール依存症)

- 飲酒自体や飲酒量をコントロールできない
- お酒のことで頭がいっぱいになり、その他への関心が極端に減る
- 飲酒が悪い結果をもたらすことを理解しながらも飲酒を続けてしまう など
「アルコール使用障害」とは、長年のアルコールの過剰摂取で、飲酒をコントロールできなくなった状態です。体内のアルコール濃度が下がると、手の震えや幻覚などの離脱症状が現れ、そこから逃れるためにさらに飲酒を続けます。その結果、家族や仕事などより飲酒を優先させ、身体的・精神的な合併症を引き起こします。治療にあたっては、無理な断酒はせず、少しずつアルコールから離れられるように、考え方や行動を変えていきます。薬物療法を行うこともあります。
薬物治療
薬物などの依存症

- 薬を飲みたいという強い欲望や強迫感がある
- 薬の用法・用量をコントロールできない
- 薬を飲まないと不安になったり、手足が震えたりする など
大麻、マリファナ、覚醒剤など、特定の薬物を繰り返し使用した結果、イライラや不快感が増強して落ち着かなくなり、その薬物を使用せずにはいられなくなる状態です。依存症になると、自分の意志では薬物の使用をコントロールできなくなってしまいます。治療は、まずは病気に対する理解を深め、薬物の調整を行います。また、対人関係や社会的な問題を抱えている方も多いため、長期的にサポートを行います。
発達障害

- 仕事や勉強がうまくできない
- 集中力がない
- 他者とコミュニケーションが取れない など
発達障害には、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害などが含まれます。これらは、生まれつき脳の働き方に違いがある点は共通していますが、同じ障害名でも特性の現れ方が違ったり、いくつかの発達障害を併せ持ったりすることがあります。行動面や情緒面に特徴があるため、生きづらさを感じることもあります。病気ではないので根本治療はありませんが、ご本人やご家族に特性に応じた過ごし方をご提案して、持っている力を活かしやすく、困難を軽減できるようサポートします。
学習障害
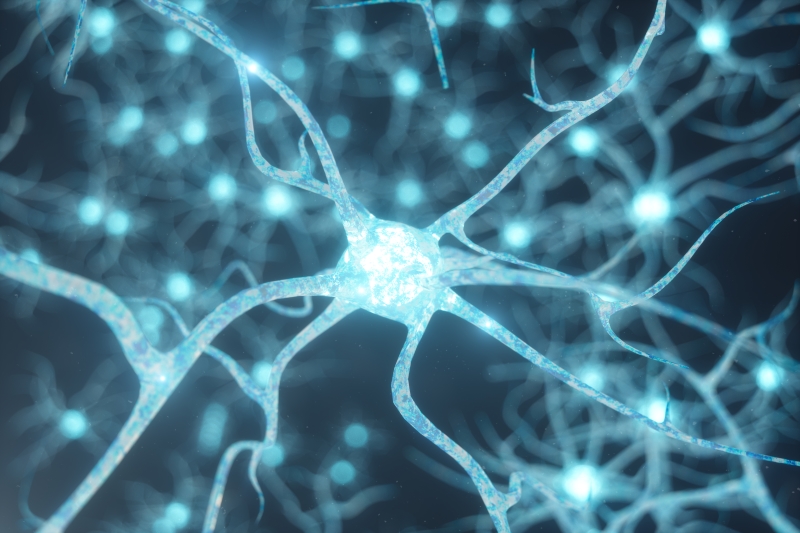
- 文字を読むことが苦手
- 文字や数字を書くことが苦手
- 簡単な計算が苦手 など
学習障害とは、全般的な知的発達に遅れがないものの、「聞く・話す・読む・書く・計算や推論する」といった能力に困難が生じた状態です。学習障害のタイプは、「読字障害」「書字障害」「算数障害」に分かれますが、症状の現れ方は人によって異なります。学習障害を根本的に治す治療方法はまだ見つかっていませんが、環境の調整を行い、苦手な分野をカバーする対策をご一緒に考えていきます。また、学習障害によってうつ病や不安障害、睡眠障害などの症状が出ている場合は、そちらの治療も行います。
休職相談

- 会社に行くのがつらい
- 会社を休みがちになっている
- 出社すると体調が悪くなる など
休職相談では、パワハラやセクハラ、長時間労働、人間関係や職場環境の悩みなど、さまざまな事情で会社に行けないという方のご相談を受けています。まずは、お薬やカウンセリングによる治療を行い、それでも改善が見込めない場合は、休職して心身ともに休養を取ることも一つの治療手段です。当クリニックでは、患者さまの状況に応じて、治療のために必要な休職期間を見極めていきます。また、職場の環境や、人間関係などに原因があれば、復職する際の条件として、部署異動などの環境調整のアドバイスも行います。
一般的な休職までの流れ
Step1:医師による診察
患者さまのご希望を踏まえた上で、休職が必要な状態であるかを判断します。
Step2:休職診断書の発行
診断書には、病名・症状・休職の期間などが記載されます。その他、会社から記載内容に指定があった場合には、診察の際にお申し付けください。
Step3:休職診断書の提出(職場の方と相談)
診断書をもとに、職場の方とご相談いただいた上で、休職(自宅療養)となることが一般的です。
Step4:休職

